
SDGs DIALOGUE

「SDGs」と言うと、実際に行動するのが難しいことのように聞こえます。でもそんなことはないのです。興味があること、やれることを身近なことから見つけてやってみる、それがSDGsには大切です。中村学園では、学生が自由な発想で興味のあることからSDGsを始めています。それは校内にとどまらず、社会へ向けた動きへと広がりを見せています。高校生、大学生の取り組みについて、久保千春学長と一緒に意見交換しました。

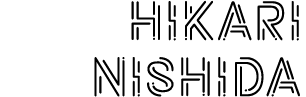

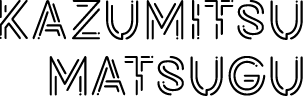

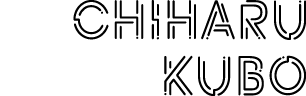

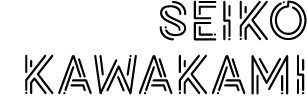
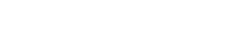

サステナビリティを目指す海外研修に参加したいという希望があり、ニュージーランド研修に参加し、高校生9人と現地スタッフで、様々な体験をしました。シュノーケリングで海の豊かさを体験したり、ニュージーランドの国鳥キーウィの保護施設を見学したり、登山をして野生の動物を見学したり、壮大な自然を体験しました。また、廃棄予定のCDプレーヤーを、全ての部品が分別できるように解体する研修も行いました。研修期間中、毎日活動後はみんなで集まってワークショップを行い、1日の体験を振り返って、何故サステナビリティを目指すのか、学びを深めました。ニュージーランド研修に参加し、日本では自然や動物への感謝が足りないと感じ、現状を変えたいと思いました。
今後は、マイボトル・マイバックを携帯する、ボランティア活動に参加するなど、自分に出来るサステナビリティを実行していきたいです。また、どの環境活動も何かしらの形でつながっていると思うので、1つ1つの環境問題の本質に向き合い、新しく学び、周囲の人に共有していきたいです。


今回の海外研修はニュージーランドの壮大な自然や環境問題に触れ、学びを深める貴重な機会となり、素晴らしい研修になりましたね。そのような体験は気づきや学びをもたらしてくれます。日常生活でその気持ちを継続させていくことが大事です。ボランティア活動を実践し、これからもSDGsに関する問題意識を持って、世界を広げていってください。
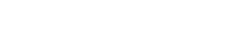


中村学園三陽中学、高等学校では「SDGs」という言葉が生まれる前から環境活動を中心に様々な社会活動に貢献してきました。14年前、一人の生徒が牛乳パック回収を始めたのをきっかけに、やがて全校生徒へと広がり様々な活動が続いています。公民館などでの小学生への環境授業、樋井川の定期清掃活動や東日本大震災、九州北部豪雨の被災地復興支援などにも取り組み、これまで「福岡市環境行動賞最優秀賞」など様々な賞をいただきました。環境活動は授業や部活動など定められた組織での活動ではなく、希望者が参加して行っています。一人では活動できなくても、みんなでやれば楽しく続けられます。今では福岡市西区の環境フェスタのボランティアなど、いろいろなところから声をかけていただくようになりました。校外の方と触れ合う機会も多く、活動で自信をつけ著しく成長する生徒もいます。今後も生徒がその可能性を発揮できるような環境を作り見守っていきたいと思っています。

一人の生徒からスタートした環境活動が学園に根付き継続されていることは大変素晴らしいことです。三陽中学、高校ではペットボトルキャップや割りばし、空き缶の回収などに積極的に取り組んでおり、そこには世界の子供たちへのワクチン供給など社会に役立てようという精神があります。地域社会への貢献も重要なことです。人のため、社会のために取り組むことは必ず自分自身にとっても大きな糧になるでしょう。
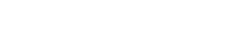

「唐津Qサババーガー」は2021年、唐津市水産業活性化支援センターにインターンシップに行った学生2人が、地元で完全養殖されている「唐津Qサバ」と人気の「からつバーガー」を組み合わせて開発したものです。「からつバーガー」さんのご協力もあり、販売したところ大変盛況でした。しかし、話はここでは終わりません。ゼミの後輩が「唐津Qサババーガー」プロジェクトを引き継ぎ、2022年は長崎県松浦市で開催された「鯖サミット」で出店。試行錯誤の末に商品を完成させ価格設定、食材調達などすべて学生が行い300個を完売したのです。このプロジェクトは次年度も引き継がれ「唐津マリンセンターおさかな村」での第3弾販売の構想があります。2人の学生から始まり代々受け継がれ広がっていく「唐津Qサババーガー」。これからも「唐津Qサバ」のブランド戦略や販路拡大に学生の力を生かせたらと考えています。


学生の情熱が感じられるプロジェクトです。「唐津Qサバ」の研究は九州大学が連携しており、企画や販売は中村学園大学が連携するというストーリーも産学官連携の象徴のような取り組みだと思います。1年だけで終わるのではなく、最初の年の学年から下の学年の学生へと引き継がれていくという点においては、まさにサステナブル(持続可能)な取り組みと言えるでしょう。