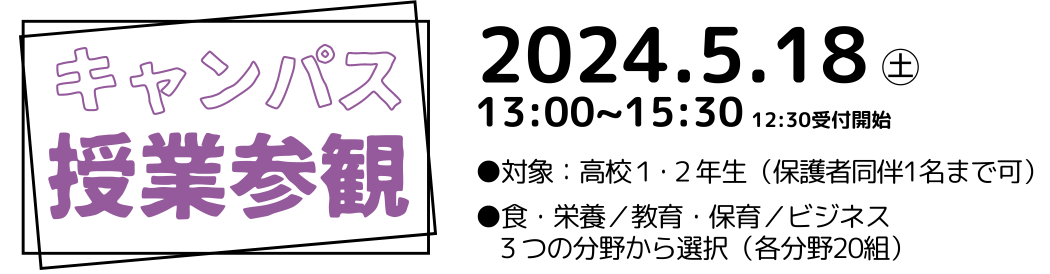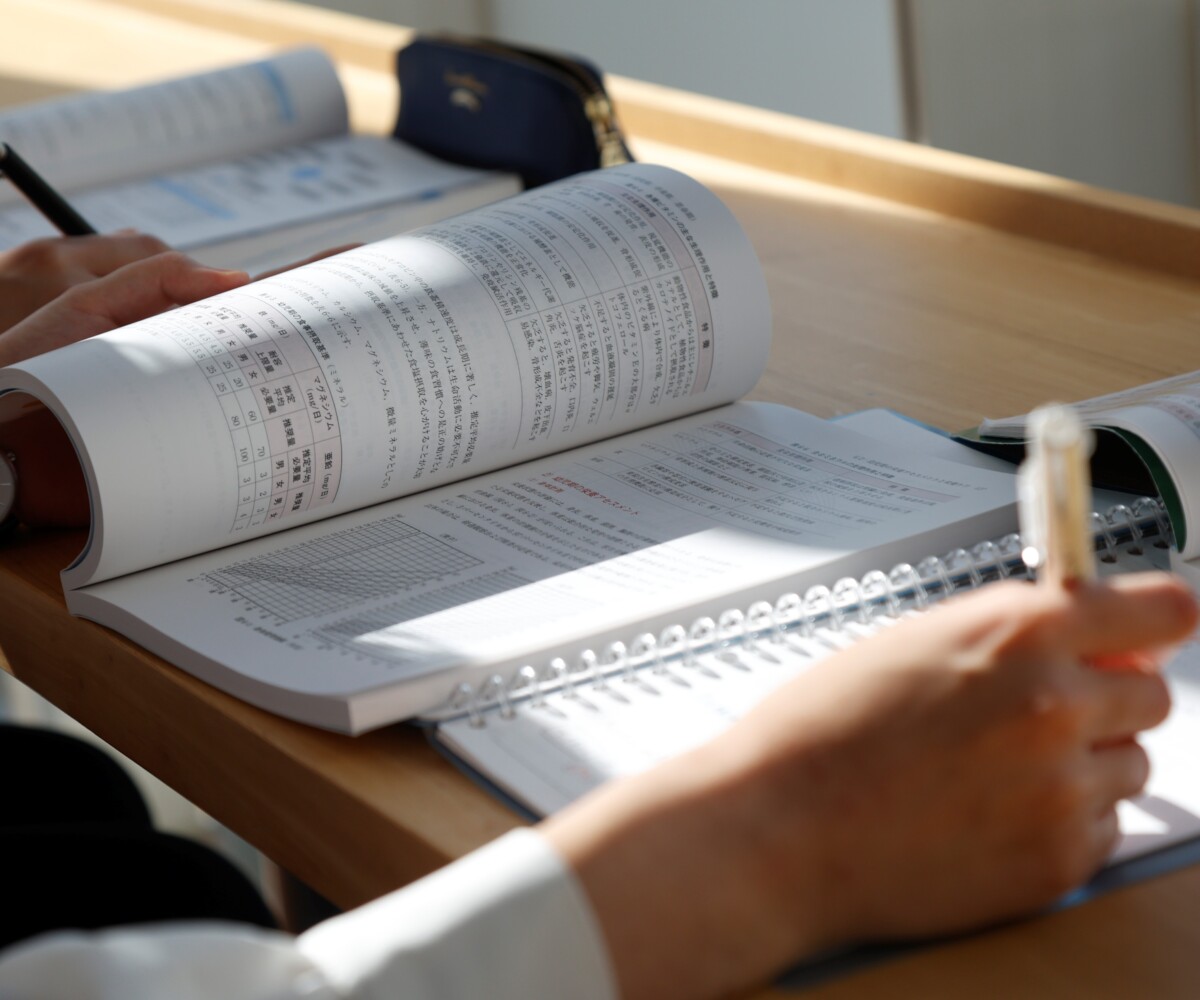能登半島ボランティア 活動証明書交付式が行われました
MENU

大学案内
学部・学科・研究科
- 学部・学科・研究科 インデックス
- 中村学園大学
- 栄養科学部 栄養科学科
- 栄養科学部 フード・マネジメント学科
- 栄養科学部 共通情報
- 教育学部 児童幼児教育学科
- 流通科学部 流通科学科
- 中村学園大学短期大学部
- 食物栄養学科
- キャリア開発学科
- 幼児保育学科
- 短期大学部 共通情報
- 短期大学部 プレカレッジ
- 他学科授業科目の履修
- 大学への編入学について
学生生活
国際交流
研究・社会連携
- 公開講座・地域連携イベント
- 研究支援
研究所・付置施設