知的好奇心は学ぶことで高まっていく。
「学ぶことは楽しい」ということを
学生たちに実感してほしい。
教育学部 児童幼児教育学科野上 俊一 教授
PROFILE九州大学大学院人間環境学府行動システム専攻博士課程単位取得後退学。博士(心理学)。2009年中村学園大学人間発達学部(現教育学部)講師として着任、2022年4月より現職。研究分野は教育心理学。本学では、「教育心理学」「心理学」等担当。
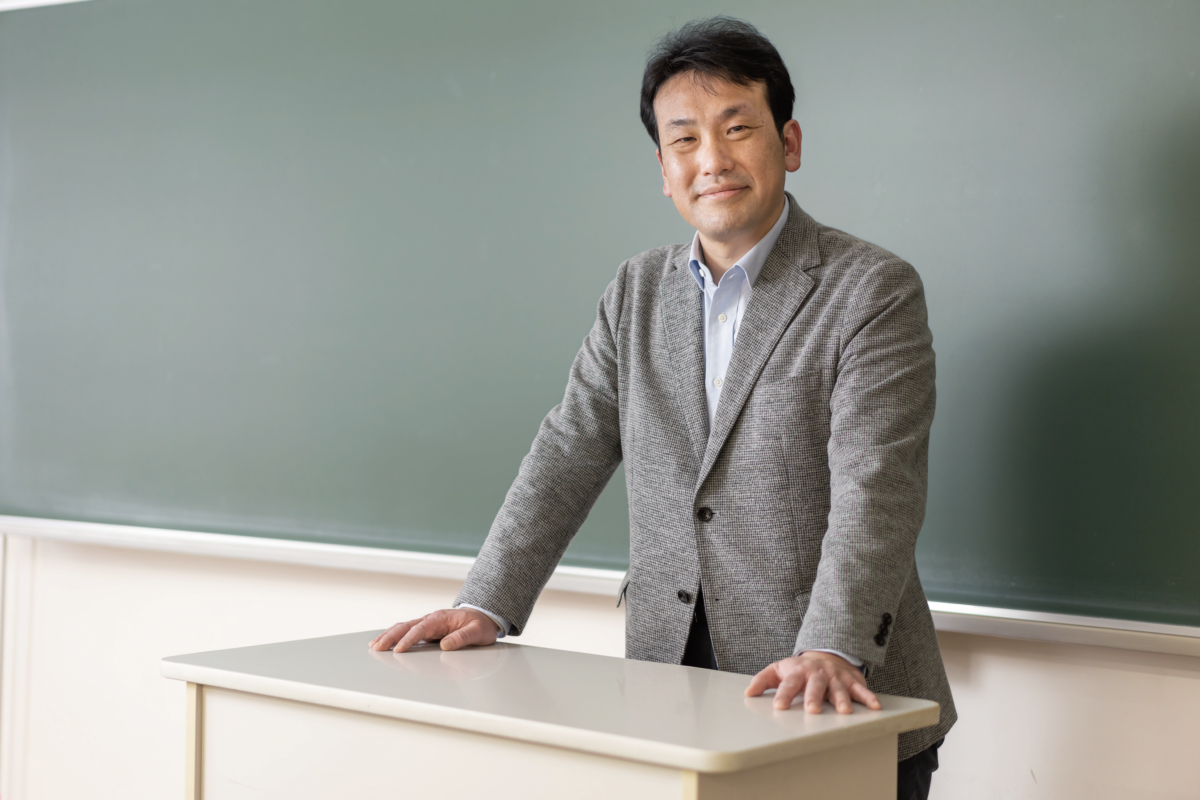
知識と知識には引力が働き、互いを引き寄せ合う―。
心理学の知見を活かした教育を進める野上俊一教授に、注力している研究やゼミの活動などをお聞きしました。
心理学の知見を活かした教育を進める野上俊一教授に、注力している研究やゼミの活動などをお聞きしました。
どんな研究に取り組まれているのですか。
専門分野は教育心理学で、現在は「知識の精緻化による知的好奇心の生起メカニズムの検討」(科学研究費助成事業)という研究を行っています。「知的好奇心」は人間が自発的に学んでいく際の大事な「エンジン」。その好奇心がどのように生まれ、どう高まっていくのか。「知っているからもっと知りたくなる」、知識が知識を引き寄せより好奇心が膨らむのではないか、ということを学術的に明らかにしようとしているところです。
以前、重点を置いていた研究テーマは「メタ認知」で、特に自己調整学習という、自身の状態を把握し、いかに自らの学習活動を調整して成果を出すかといった、個人内で完結する過程に目を向けていました。そこから知的好奇心にシフトしていったのは、次第に、人は一人では乗り越えられないことも多く、いろいろな人と関わって知的にも人間的にも賢くなるという考えが強くなってきたからです。もう一つの研究の柱に「協同学習」を据え、互いに学び合い、教え合い、高め合う学習法の研究と教育実践に取り組んでいます。実際に学生を見ていると、協力しながら相互に成長していきます。その中で重要なのは人間関係を作っていく力とさまざまなことに興味を抱いていく好奇心であることがよく分かります。
私が一連の研究を通して一番学生に伝えたいのは「何かを学ぶことは楽しい。新しい経験をして知らなかった世界が開かれることを楽しもう」ということ。それを子どもたちに伝えられる教員や保育者になってほしいと願っています。
以前、重点を置いていた研究テーマは「メタ認知」で、特に自己調整学習という、自身の状態を把握し、いかに自らの学習活動を調整して成果を出すかといった、個人内で完結する過程に目を向けていました。そこから知的好奇心にシフトしていったのは、次第に、人は一人では乗り越えられないことも多く、いろいろな人と関わって知的にも人間的にも賢くなるという考えが強くなってきたからです。もう一つの研究の柱に「協同学習」を据え、互いに学び合い、教え合い、高め合う学習法の研究と教育実践に取り組んでいます。実際に学生を見ていると、協力しながら相互に成長していきます。その中で重要なのは人間関係を作っていく力とさまざまなことに興味を抱いていく好奇心であることがよく分かります。
私が一連の研究を通して一番学生に伝えたいのは「何かを学ぶことは楽しい。新しい経験をして知らなかった世界が開かれることを楽しもう」ということ。それを子どもたちに伝えられる教員や保育者になってほしいと願っています。
ゼミの活動について教えてください。
いろんな経験が知的好奇心にもつながるので、何にでもチャレンジするのがゼミのモットーです。レシピコンテストや読書感想文コンクールなど学内のコンテストには全員に応募を呼びかけます。高大接続探求学習ワークショップなどのイベントも積極的に参加しています。
年に4回、近郊の低山に登るのも恒例行事です。皆で山頂に到達するという目標を共有して、助け合いながらやり遂げる体験は協同学習にも通じるものです。
また、ゼミ生には2年間で100冊の読書も課しています。読書を通して知識が増えるほど見えてくる世界も違ってくるからです。ここ数年は、哲学者・教育者の森信三(1896ー1992)が教育観や教師自身の生き方を説いた『修身教授録』を全員で読み進めながら、どの部分が今の自分に響いたか、それはなぜかなどを話し合っています。修身とは、自分で自分の身を修めること。自己調整するという点でメタ認知にも繋がります。この本を読む中で、自己調整力による個の成長を基本とし、それが備わっている人たちが協力し合えば、社会の諸問題に対してより良い解決策が生まれるという理解を育んでいけたらと思います。
年に4回、近郊の低山に登るのも恒例行事です。皆で山頂に到達するという目標を共有して、助け合いながらやり遂げる体験は協同学習にも通じるものです。
また、ゼミ生には2年間で100冊の読書も課しています。読書を通して知識が増えるほど見えてくる世界も違ってくるからです。ここ数年は、哲学者・教育者の森信三(1896ー1992)が教育観や教師自身の生き方を説いた『修身教授録』を全員で読み進めながら、どの部分が今の自分に響いたか、それはなぜかなどを話し合っています。修身とは、自分で自分の身を修めること。自己調整するという点でメタ認知にも繋がります。この本を読む中で、自己調整力による個の成長を基本とし、それが備わっている人たちが協力し合えば、社会の諸問題に対してより良い解決策が生まれるという理解を育んでいけたらと思います。
何かを学ぶことは楽しい。新しい経験をして知らなかった世界が開かれることを楽しもう。
今後の抱負などについてお聞かせください。
「知識の精緻化による知的好奇心の生起メカニズムの検討」の研究にめどをつけ、さらに自分の友達や好きな有名人などが興味持っていることに自分も興味を持つといった、社会的な文脈で起こる知的好奇心の研究に発展させていけたらと考えています。
また、これまでも授業の中に、協同学習を取り入れてきましたが、今春からの新カリキュラムでは、3年生の選択科目として「協同学習」を開講します。10年ほど前にアクティブ・ラーニング推進が謳われ始め、対話型の協同学習が注目され数多く取り組まれてきました。今、まさに真価が問われるときなので、しっかり取り組んでいきたいです。
また、これまでも授業の中に、協同学習を取り入れてきましたが、今春からの新カリキュラムでは、3年生の選択科目として「協同学習」を開講します。10年ほど前にアクティブ・ラーニング推進が謳われ始め、対話型の協同学習が注目され数多く取り組まれてきました。今、まさに真価が問われるときなので、しっかり取り組んでいきたいです。


