本学科ならではの研究テーマを見つけ
実験に重点を置きながら
学生の多様な未来の応援を。
栄養科学部 栄養科学科信久 幾夫 教授
PROFILE九州大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了、博士(理学)。1997年より九州大学大学院医学研究科にて日本学術振興会特別研究員を務めた後、2000年より熊本大学発生医学研究センター転写制御分野にて助手、講師。
2009年より東京医科歯科大学難治疾患研究所幹細胞制御分野にて准教授として勤めた後、2021年4月より中村学園大学栄養科学部栄養科学科教授に就任。研究分野は分子生物学、発生生物学、栄養生化学。
2009年より東京医科歯科大学難治疾患研究所幹細胞制御分野にて准教授として勤めた後、2021年4月より中村学園大学栄養科学部栄養科学科教授に就任。研究分野は分子生物学、発生生物学、栄養生化学。
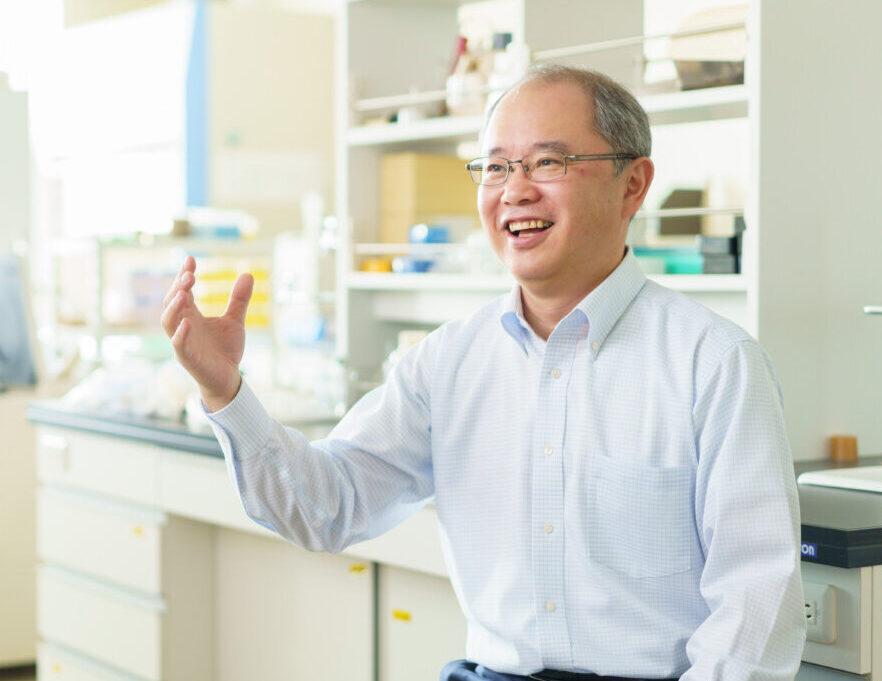
造血幹細胞についての研究に取り組み、
その成果が注目されている信久 幾夫 教授。
詳しい研究内容やゼミ活動の特徴、今後の方針などについてお聞きしました。
その成果が注目されている信久 幾夫 教授。
詳しい研究内容やゼミ活動の特徴、今後の方針などについてお聞きしました。
どんな研究に取り組まれているのですか。
専門分野は分子生物学や発生生物学で、骨髄の中で全ての血液をつくる造血幹細胞(血液幹細胞)の研究に取り組んできました。造血幹細胞は胎仔の時に大動脈の中で生まれることが知られており、そこでどういう分子が関わり増幅していくのかをマウスを用いて探ってきました。その結果、たくさんの分子をつくる元となるタンパク質「転写因子」が関係していることが分かったのです。
造血幹細胞で最大の問題と言えるのが、他の幹細胞と異なり生体外で増やせないことです。私たちは研究を進め、培養皿上で血液細胞塊(血液細胞の集合体)構成細胞に転写因子の一つである「Sox17」を導入すると、血液細胞が増えることを示しました。さらにSox17が発現を促す様々な遺伝子が、造血幹細胞を含む血液細胞塊の増殖に寄与することも明らかにしました。
もし、生体内の造血幹細胞と同じ能力を持つ造血幹細胞を生体外で増やすことができるようになれば、血液疾患治療のための骨髄バンクは不要になります。しかし血液は複雑で難しい部分が多く、それを実現するのは容易なことではありません。私たちの研究成果が血液疾患治療の可能性を少しでも広げることになればうれしい、というところです。
造血幹細胞で最大の問題と言えるのが、他の幹細胞と異なり生体外で増やせないことです。私たちは研究を進め、培養皿上で血液細胞塊(血液細胞の集合体)構成細胞に転写因子の一つである「Sox17」を導入すると、血液細胞が増えることを示しました。さらにSox17が発現を促す様々な遺伝子が、造血幹細胞を含む血液細胞塊の増殖に寄与することも明らかにしました。
もし、生体内の造血幹細胞と同じ能力を持つ造血幹細胞を生体外で増やすことができるようになれば、血液疾患治療のための骨髄バンクは不要になります。しかし血液は複雑で難しい部分が多く、それを実現するのは容易なことではありません。私たちの研究成果が血液疾患治療の可能性を少しでも広げることになればうれしい、というところです。
ゼミではどういう活動をしていますか。
ゼミは実験を柱にしており、時にはマウスも使い分子・細胞生物学手法を用いていろんな解析を行っています。現在の学生の卒論テーマは大きく3つあります。その一つが「オートファジー(細胞の自食作用)」で、オートファジーの過程において私が注目している分子の詳しい働きを研究しています。また「幹細胞とキノコの関わり」ではキノコの熱水抽出物が神経幹細胞に与える効果などを、「Sox17とDNAの結合」では転写因子Sox17とDNAが結合しタンパク質がつくられているかなどを調べています。
学生と細やかにコミュニケーションを取り、丁寧で分かりやすい指導を心がけています。調理実習の経験が豊富なせいか、学生は一様に手先が器用で、共同作業も得意です。実験でも自然と役割分担ができてスムーズに進められています。
解析機器の技術革新が目覚ましく、これまでは不明だった栄養学と生命現象の結びつきもいろいろと明らかになってきています。そういう意味では、幹細胞と栄養学の関わりはますます注目されていく領域だと思います。
学生と細やかにコミュニケーションを取り、丁寧で分かりやすい指導を心がけています。調理実習の経験が豊富なせいか、学生は一様に手先が器用で、共同作業も得意です。実験でも自然と役割分担ができてスムーズに進められています。
解析機器の技術革新が目覚ましく、これまでは不明だった栄養学と生命現象の結びつきもいろいろと明らかになってきています。そういう意味では、幹細胞と栄養学の関わりはますます注目されていく領域だと思います。
解析機器の技術革新が目覚ましく、これまでは不明だった栄養学と生命現象の結びつきもいろいろと明らかになってきています。そういう意味では、幹細胞と栄養学の関わりはますます注目されていく領域だと思います。
これからの抱負をお聞かせください。
まず造血幹細胞に関する未発表の研究論文を仕上げ、今後は本学ならではの研究テー
マを見つけ、実験、研究の軸にできればと考えています。
また、学生の指導においては、私が今まで蓄積してきたことを活かしたいと思っています。栄養科学科の学びは、基本的には管理栄養士になるためのものであり、その内容は栄養学、解剖学、生化学など多岐にわたり、実験、実習など実践的な内容も多くあります。こうした学びをきっかけに、学生の感じた興味を大切にして、多様な可能性を育むサポートをするのも自身の役割だと捉えています。
ゼミでは、卒業論文指導はもちろんですが、実験の作業や話し合いを通して関わりを深め、実験・研究が楽しかったと思ってもらえるようにバックアップしていきたいと考えています。
マを見つけ、実験、研究の軸にできればと考えています。
また、学生の指導においては、私が今まで蓄積してきたことを活かしたいと思っています。栄養科学科の学びは、基本的には管理栄養士になるためのものであり、その内容は栄養学、解剖学、生化学など多岐にわたり、実験、実習など実践的な内容も多くあります。こうした学びをきっかけに、学生の感じた興味を大切にして、多様な可能性を育むサポートをするのも自身の役割だと捉えています。
ゼミでは、卒業論文指導はもちろんですが、実験の作業や話し合いを通して関わりを深め、実験・研究が楽しかったと思ってもらえるようにバックアップしていきたいと考えています。


