歴史を通して、
子どもの自由な表現を大切にした
音楽のあり方を探っていく。
短期大学部幼児保育学科松園 聡美 准教授
PROFILE広島大学教育学部教科教育学科音楽教育学専修卒業。福岡大学大学院人文科学研究科教育・臨床心理専攻博士課程後期単位取得満期退学。修士(教育学)。専門は教科教育学・音楽教育学。本学では、「保育内容表現(音楽)」「幼児と表現(音楽)」「幼児保育演習」等担当。全国大学音楽教育学会、日本学校音楽教育実践学会など、関連学術団体の理事、役員等を務めている。
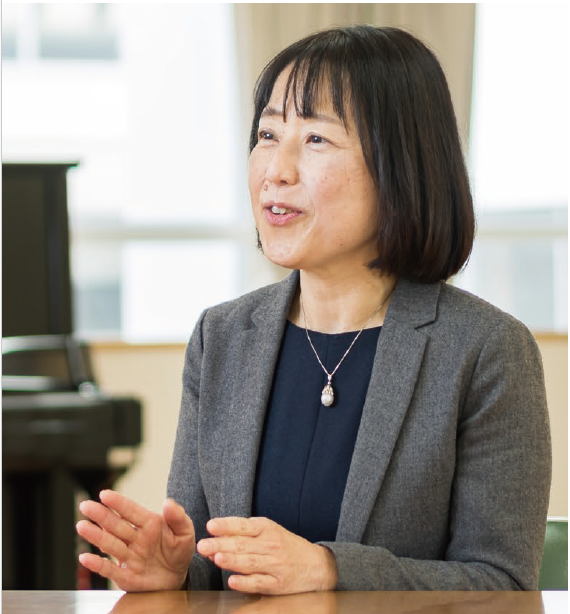
「本来、音楽の授業は楽しいもの」という思いを抱き、音楽教育のルーツを辿る松園 聡美 准教授。
研究内容やゼミ活動などについて、いろいろと伺いました。
研究内容やゼミ活動などについて、いろいろと伺いました。
取り組まれている研究について教えてください。
もともとわらべうたの採譜などを行い、幼児の遊びと音楽との関わりについて研究してきました。常に保幼小接続の視点から子どもと音楽をどう捉えていけばいいのかを考えています。その根底には、技術面ばかりを重視するのではなく、子どもたちが自由に表現することも尊重されるべきでは、という問題意識があります。
今は、音楽教育の歴史について研究しています。なぜ現在の音楽教育があるのかを考える上で、歴史認識は避けて通れません。そこで今は、明治10年代に音楽(唱歌)教育展開の契機となったと思われるいくつかの出来事と、それを起点とした教員養成への流れを分析しています。
当時、全国各地の教員が東京に招集され最新の教育法を学びました。ほとんどの教員に音楽的素養はなく、未知だった音楽を勉強して地元に帰り音楽教育を始めたのです。音楽の専門家ではなかった教員が、普通教育の中で子どもたちに音楽をどのように伝えていたのか。この音楽教育の始まりを理解することは、そもそも子どもと音楽はどのようにつながっていけばいいのかという答えに通じると考えています。福岡で初めて音楽教育を行ったとされる教員についても調査を進めているところです。
音楽の授業は本来、楽しみながら取り組めるものだと考えています。音楽の授業を自ら工夫し、変化に対応する教育者の養成を目指して、これらの研究の考え方を活かしていきたいと思います。
今は、音楽教育の歴史について研究しています。なぜ現在の音楽教育があるのかを考える上で、歴史認識は避けて通れません。そこで今は、明治10年代に音楽(唱歌)教育展開の契機となったと思われるいくつかの出来事と、それを起点とした教員養成への流れを分析しています。
当時、全国各地の教員が東京に招集され最新の教育法を学びました。ほとんどの教員に音楽的素養はなく、未知だった音楽を勉強して地元に帰り音楽教育を始めたのです。音楽の専門家ではなかった教員が、普通教育の中で子どもたちに音楽をどのように伝えていたのか。この音楽教育の始まりを理解することは、そもそも子どもと音楽はどのようにつながっていけばいいのかという答えに通じると考えています。福岡で初めて音楽教育を行ったとされる教員についても調査を進めているところです。
音楽の授業は本来、楽しみながら取り組めるものだと考えています。音楽の授業を自ら工夫し、変化に対応する教育者の養成を目指して、これらの研究の考え方を活かしていきたいと思います。
ゼミ活動の特徴を教えてください。
ゼミでは「子どもと音楽」をテーマとして、保育者を目指す学生が、歌を歌いながら身体を動かして表現したり、楽器を演奏したり、ダンスを行うなど、実践的な活動を行っています。保育者を目指す学生が、歌を歌いながらの遊び、楽器演奏、ダンスなど実践的な活動を行っています。私が細かく指導するのではなく、選曲や振りつけ、練習など学生たちが主体的に進めていきます。そのまとめとして、福岡市内の保育園を訪問して発表会を行っています。
2023年度はハンドベルの演奏と「ジャンボリミッキー!」のダンスを披露しました。子どもたちが一緒に踊ってくれるなど盛り上がり、学生たちも達成感に包まれていた様子でした。荒江保育園の子どもたちがお礼にと歌を2曲歌ってくれるというサプライズもあり、学生たちはいっそうやりがいを感じたようです。みんなで一生懸命取り組んだものに子どもたちが応えてくれた。学生にとってこの経験は、就職先の保育現場でも子どもたちとこうして歌やダンスを楽しもう、というモチベーションの醸成にもなったことでしょう。
2023年度はハンドベルの演奏と「ジャンボリミッキー!」のダンスを披露しました。子どもたちが一緒に踊ってくれるなど盛り上がり、学生たちも達成感に包まれていた様子でした。荒江保育園の子どもたちがお礼にと歌を2曲歌ってくれるというサプライズもあり、学生たちはいっそうやりがいを感じたようです。みんなで一生懸命取り組んだものに子どもたちが応えてくれた。学生にとってこの経験は、就職先の保育現場でも子どもたちとこうして歌やダンスを楽しもう、というモチベーションの醸成にもなったことでしょう。
音楽の授業は本来、楽しみながら取り組めるもの。
授業を自ら工夫し変化に対応する教育者の養成を目指して、研究の考え方を活かしたい。
授業を自ら工夫し変化に対応する教育者の養成を目指して、研究の考え方を活かしたい。
これからの抱負についてお聞かせください。
ゼミ活動では、いろんな楽器を使って子どもの歌と合わせる、それをダンスとコラボさせる、ハンドベルと他の楽器で合奏するなど、もっと活動を多彩に展開していけたらと思っています。それに加えて、発表の場を幼稚園やいろんな施設にも広げていきたいです。またゼミで以前、取り組んでいた「手遊びブック」の制作も復活させられたらと考えています。
私が所属する全国大学音楽教育学会では、今年8月、全国大会が福岡で開催されます。九州地区学会の役員として大会運営に力を尽くしたいと思っています。大会プログラムは、研究演奏会、講演会、ワークショップなどで、子どもの感性を育む音楽教育について学びます。会員以外の方も参加できるので、ぜひ、保育を学ぶ学生にも足を運んでもらえればと思います。
私が所属する全国大学音楽教育学会では、今年8月、全国大会が福岡で開催されます。九州地区学会の役員として大会運営に力を尽くしたいと思っています。大会プログラムは、研究演奏会、講演会、ワークショップなどで、子どもの感性を育む音楽教育について学びます。会員以外の方も参加できるので、ぜひ、保育を学ぶ学生にも足を運んでもらえればと思います。


