
-
管理栄養士として
「チーム医療」で患者さんに
寄り添います-
桜十字福岡病院
松上 ともかさん - 栄養科学部 栄養科学科 卒業
-
桜十字福岡病院
管理栄養士の資格を取得して希望通り保育園と病院に勤務
小さい頃から食に興味があり、管理栄養士の合格率が全国でも高い中村の栄養科学科に進学しました。卒業後は子どもの食に関わる仕事がしたいと思い、保育園に2年勤めた後、次は高齢者や病気を抱えている人をサポートしたいと考えて、こちらの病院に転職しました。初めての病院勤務でしたが、本学出身の先輩が何人もいて、とても心強く感じました。
患者さんが回復していく姿がうれしくてやりがいを感じる
今は、回復期リハビリ病棟の患者さん50 人ほどの栄養管理を担当しています。脳梗塞など脳の血管に障害が起きた人や骨折した人が、退院に向けてリハビリを行う病棟です。10代から90代まで幅広い年齢の患者さんがいて、体の状態や持病、アレルギーなどによって、提供する食事はさまざまです。患者さん一人ひとりの話を聞きつつ、ドクターとナース、リハビリ担当者と密に連携し、チームで患者さんをサポートしています。
この仕事の魅力は、最初のうちは重度で鼻や血管から栄養をとっていた方が、リハビリによって口から食べられるようになる過程に関われることです。また、精神的に落ち込んで食べられない患者さんと話す中で、少しずつ信頼関係ができて、「あなたが来てくれるから今日は食べたよ」と食べ終わったお皿を見せてもらったりすると、うれしくてやりがいを感じます。これからも資格と経験を活かして、人の成長や健康を支えていきます。


-
商品開発者のこだわりを
消費者に届ける橋渡し-
株式会社ピエトロ
野上 鈴奈さん - 栄養科学部 フード・マネジメント学科 卒業
-
株式会社ピエトロ
正確かつ効果的なパッケージに仕上げるために商品開発者と対話を重ねる
職場では冷凍商品やパスタ関連商品、デリカ(惣菜)商品のパッケージデザインのディレクションや販促物の企画立案など、マーケティングに関わる全般を担当しています。開発担当とその商品の特長や魅力が何かを対話を重ねながら深掘りし、それをお客様に効果的に伝わるデザインや言葉として落とし込んでいくのが腕の見せどころです。ときには50案のキャッチコピーを考え選ぶこともあり、どれがベストなのか頭を悩ませます。パッケージの制作には正確で緻密な商品の知識とマーケティング的な視点の両面が必要ですが、大学時代に取得した食品表示診断士の資格がその素地となっていると感じます。

食に特化したユニークな授業の数々がマーケティングの世界へ導いた
「食に関する職に就きたい」と漠然とした理由で入学した大学でしたが、食品業界で働く方による最前線のフードビジネスの講義や、テーマに沿った商品開発を立案する授業など、食に特化した特色のある授業を経て、次第に自分の将来像が定まってきました。ダブルスクールに通って調理師免許を取得するクラスメートに感化され、色彩検定試験に向けて勉強した経験も、現在の仕事に直結する糧になったと思います。将来の目標はパスタ関連商品など、自分が関わった商品のブランド価値をさらに押し上げていくこと。そのためにもプライベートでも貪欲に優れたアイデアを吸収し、自社のマーケティングに活かしたいと思います。

-
生活のおもしろさや豊かさが
生徒たちに伝わるように-
福岡教育大学附属久留米中学校
長 航平さん - 栄養科学部 栄養科学科 卒業
-
福岡教育大学附属久留米中学校
元家庭科教諭の先生による大学での実践的な講義はそのまま今の支えに
中学生の頃から教師に憧れていて、食べることも好きだったので、両方をめざせる本学に進学しました。大学の授業では家庭科教育法の模擬授業が特に印象に残っています。先生ご自身が家庭科教諭の経験がおありだったので、実践的な授業ばかりでした。早い段階から模擬授業に取り組み、どうしたら生徒たちの興味を引き出すことができるのかを深めていけたことは、私の基盤となっています。調理実習や被服などの実習も多くあり、現在も役立っています。
調理の楽しさを知った子どもたちが成長する様子を間近で感じられる
中高の家庭科教諭と栄養教諭の教員免許を取得したので、キャンパスライフは目まぐるしかったですが充実していました。共に学んだ友達の存在は大きく、今も連絡をとりあっています。現代の私たちの暮らしは多様化しています。食事を例に挙げると外食は当然のこと、デリバリーサービスも利用可能で、選択の幅は広がっています。しかし食は作る楽しみがあり、作った料理で人を喜ばせることができます。家庭科を通じて、そんな生活のおもしろさを生徒に伝えたいですね。実習で作った料理を「家でも作ってみたよ」などといわれるとうれしいです。生徒たちに何かを手渡していけること、目の前でその変化を感じられること、それが家庭科教諭の醍醐味だと思っています。


-
お客様が抱える課題を
知識と味覚で解決に導く-
一番食品株式会社
椛島 奈央さん - 栄養科学部 フード・マネジメント学科 卒業
-
一番食品株式会社
学生時代に幅広く吸収した知識が、商品開発で即戦力として働く土台となった
食に関する幅広い知識を得たいと思い本学科を選択。調理やマネジメント、食の安全性など多角的な知識や技術が習得できたことに加え、企業から招いた講師による実践的な知見や資格取得のためのノウハウが得られるのも魅力でした。現在の職場ではクライアントが求める美味しさをオーダーメイドで作り出す商品開発を担当。お客様が求める味はもちろん、隠れた課題まで探り出し、解決策を提案することを心がけています。入社3年目と社歴は浅いですが若手の活躍を後押しする土壌があり、多くの商品開発を担当します。売り場に商品が並ぶ様子を見るたびやりがいを感じますね。

科学的な知識と自分の舌の感覚を掛け合わせ、理想の味を見つけ出す
味づくりにはさまざまなアプローチがあり、そのひとつに目指す味に似た商品の食品表示を参考にする方法があります。原材料や栄養成分の表示からは味を決める重要なヒントが得られます。大学時代に取得した食品表示診断士の資格は現在の仕事にも活きていますね。そうした多角的な知識に加え、最終的には社内でベロ(舌)メーターと呼ばれる感覚を頼りに理想の味を見つけるのも面白いところです。また現在、中村学園事業部や福岡県との「宇宙日本食」の開発にも参加しています。いつか自分が携わった食が宇宙に飛び立つ。そんな夢のある仕事に就けて幸せですね。


-
行政の立場で広く
食の大切さを伝える仕事-
福岡県保健医療介護部
猿渡 りささん - 栄養科学部 栄養科学科 卒業
-
福岡県保健医療介護部
食を通じた貢献がより広域でできることを、大学の学びで知る
料理上手な母の影響で、小さいころから食に関心をもっていました。小学生のときには料理教室にも通い、両親や祖父母に料理をふるまっているうちに、食で社会のために力を尽くしたいという気持ちが膨らんできました。そして管理栄養士の資格も取得したいと思い、中村を志望しました。ゼミでは、久山町の公衆栄養の調査に携わりました。その過程で、行政の立場なら地域と関わりながら貢献できると知ったのが今の道を目指したきっかけです。
若いうちから減塩を意識してもらうため、高校で出前事業を企画
所属する係では減塩普及事業であるスマートにソルトをつかう減塩プロジェクト、略して「TRY!スマソる?」を推進しています。減塩レシピを公募し、企業協力のもと減塩の弁当を販売するなどしています。ほかに減塩をテーマにした市民講座や学校栄養士が対象の講座も担当しています。「TRY!スマソる?」事業は3年目ですが認知度が上がってきているのを実感していて、県全体という広域に働きかけられることをやりがいに感じています。減塩は若い世代から意識することが大事です。先日はゼミの恩師に協力を依頼して、学生が講師となって高校の出前事業を企画しました。先生とのつながりが今もあるからできたこと。このあたたかい関係性も中村ならではですね。


-
幅広い食材の知識を吸収し
巨大な市場を開拓する-
ヤマエ久野株式会社
原田 直明さん - 栄養科学部 フード・マネジメント学科 卒業
-
ヤマエ久野株式会社
美味しいだけでない付加価値を見つけ、その商材を取引先企業の課題解決に繋げる
大学で幅広い学問を学ぶなかでさまざまな食材を扱いたいと思い、卸売業の世界を選びました。現在は大手コンビニエンスストアのおにぎりや惣菜を製造する工場に、その原材料を供給する仕事を担当しています。工場から指定された原料を納めるほか、魅力ある原材料を探し出しそれを新規提案することも。実は工場で味と分量のブレがなく調理することは設備や人件費もかかる課題なのですが、その“困りごと”をクリアする加工肉を提案したところ見事に“刺さって”商品化に。九州山口のたくさんの店舗で販売されました。そんなスケール感のある仕事ができることも醍醐味ですね。
食はさまざまな要素で成り立つため、自分のあらゆる経験を活かすことが可能
大学時代、オーストラリアに1年間留学しました。その際に身につけたコミュニケーション能力は、商談の際にも活きていると思います。製造業のスペシャリストとの商談は難しさもありますが、SNSを活用したトレンドのキャッチという面では若い私にも強みがあり、そうした提案を求められる場面も多いです。また、マーケティングの授業で学んだ新しい需要を掘り起こす手法や、色彩検定で得た色彩感覚など、大学内外で取り組んだ学びは大きいですね。定期的に工場の視察を行いますが、その際に職人の方のこだわりを直接聞けることは刺激的で学びにもなります。

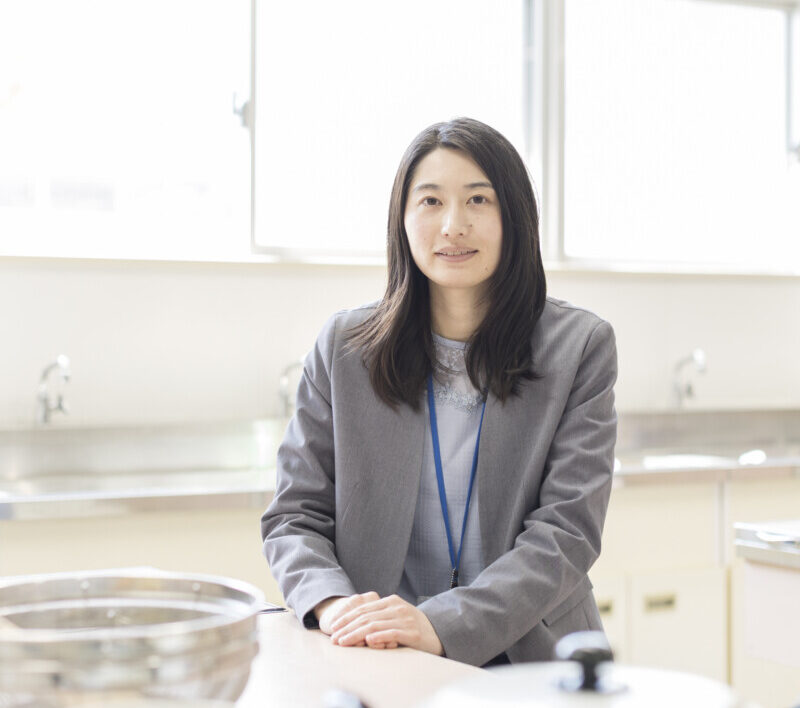
-
小学校での食育で
「生きる力」を-
大野城市立 月の浦小学校(栄養教諭)
中西 菜月さん -
2017年
栄養科学部 栄養科学科 卒業
-
大野城市立 月の浦小学校(栄養教諭)
大学3年生の時、大量調理の実習で小学校に行き、栄養教諭を目指しました。現在は献立作成・発注などの給食管理、授業や委員会活動、「お弁当の日」などを通じて、食育に取り組んでいます。栄養教諭は各学校に1名ずつ配置される一人職。同僚に自分のしたいことや、力を貸してほしいことを理解してもらえる関係づくりを大事にしています。仲間の大切さを感じたのは大学時代。教職を目指す仲間と出会い、切磋琢磨した経験があるからです。教員採用試験の前には一緒に勉強をしたり、不安な気持ちを分かち合ったりした一生の仲間です。今の時代に求められる「生きる力」に、食は欠かせない要素。幼い頃からの食習慣が豊かなものになるよう、子どもたちと関わっていきたいです。

-
在学中に触れた
多様な価値観が
自分を見つけるきっかけに-
株式会社マイナビ
楠八重 真衣さん -
2019年
流通科学部 流通科学科 卒業
-
株式会社マイナビ
自社の採用担当として新卒・キャリア採用の面談・面接、インターンシップ運営、内定者研修などを行っています。「会社の経営資源である『人』に携わりたい」という思いから、この会社を選びました。高校時代に自分の未来の姿がイメージできず悩んでいた際、「ナカムラでやりたいことを見つけましょう!」という学校案内のキャッチコピーを見て、中村学園大学で将来を考えたいと思うようになりました。在学中は、PCスキル・日商簿記・ファイナンシャルプランナーの資格取得、地域活性活動を行うゼミ活動、栄養や教育の授業を履修するなど、様々な分野に興味を持ち、挑戦していました。多くの価値観に触れたことが、自分の価値観を作り、今の仕事につながっていると思います。

-
栄養士だけじゃない!
食にまつわる幅広い仕事を
目指せるのがナカムラ-
株式会社マルタイ
坂本 愛鈴さん -
2022年
栄養科学部 フードマネジメント学科 卒業
-
株式会社マルタイ
食べることが好きで、なにか「食」に関わる仕事に就きたいと思っていたところ大学受験のときにナカムラを知りました。管理栄養士になりたいというより、食や栄養について学びたいという思いが強くフード・マネジメント学科を選びました。現在は「マルタイ」で即席麺などの新商品の味を作ったり、工場で生産するための説明書を作成したりしています。大学生活は今の自分を作ってくれた恵まれた時間でした。食へのアンテナが高く、食を大事にする友人たちからは学ぶことが多く、今でも商品開発の悩みを相談し合う仲間です。これからも食への興味を大事にし、自分の作る新商品が誰かの笑顔に繋がるよう日々励みたいと思います。

-
トライ&エラーを重ね
さらに美味しいパンを
より多くの方々に-
BAKERS’ MARKET
藤吉 航生さん - 流通科学部 流通科学科 卒業
-
BAKERS’ MARKET
知識を結果につなげる実行力の大事さを学んだ
経営や商学などを幅広く学びたいと思い、中村の流通科学部を選びました。どの先生も親身になって指導してくださりありがたかったです。いろんな学びの中でも特に心に刻まれたのは、修得した様々な知識をトライ&エラーを繰り返しながら結果につなげていく実行力の大事さ。そのことは前職の会社員だった時も、ベーカリー「BAKERS’ MARKET」の2代目としてパン職人になった現在も、私の軸となっています。
大学時代の大きな思い出は、東南アジアを一人で旅して現地の人の暮らしに触れたこと。そんなにお金がなくても気持ちの部分で豊かさがあればハッピーで、自分なりに毎日を楽しむことが大切だと気づかされました。美味しいパンでたくさんの人の日常に楽しさを添えられたら嬉しいですね。

パン作りの腕を磨きつつ続々と新商品を開発中
BAKERS’ MARKETは両親が2004年に創業。国産小麦と自家製酵母を使った体に優しいパンにこだわり、地域の方々に支えられながら年月を積み重ねてきました。当初は後継者になるつもりはなかったのですが、両親も歳を取ってきて、自然に店を継ぎたいと思うようになりました。
パン職人になって2年。両親に教わりながら、トライ&エラーを重ね腕を磨いています。そんな中でライ麦を使った甘じょっぱい「メープルナッツベーコン」や、もちと明太子が詰まった「もちめんたい」など、新商品も開発しました。中村で学んだマーケティングやネーミングなども仕事に役立っていますね。店は2024年で創業20周年。両親が培ってきたものをちゃんと継承し、新しい感覚も投入しながら、これから10年、20年と進んでいきたいです。
※中村学園大学同窓会誌「山河」より素材提供



