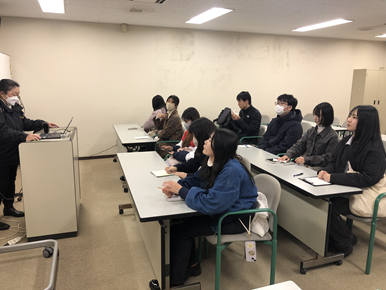ハウステンボスのSDGSへの取り組みから環境会計を学ぶ(環境施設の説明と視察を含む)
日野ゼミでは、これまでに過去14年間のハウステンボス株式会社の財務諸表の分析と再建のための取り組みについて調査研究を行ってきました。当該企業はかつて、赤字からのV字脱却を成し遂げた企業です。このアクティブラーニングは、ハウステンボス株式会社を実際に訪問することにより、理論と実際の融合を図るものです。特にSDGSについて考察することが柱となっています。つまり、現実の環境対策から環境報告書を考えてみるというもので、会計の分野の中でも環境会計に該当します。
学生の事後レポート
学生Tさん:ハウステンボス研修を終えて学んだことは、ハウステンボスのSDGsの取り組みとして、水の浄化で最終的に人がその水を飲めるぐらい、安全にすることを心掛けているというお話を聞いて、現代の世の課題にしっかり向き合っていることが分かった。
また、街の維持と安全てとして、なるべく危険な部分があるものは、共同溝に埋め込んでいるという対策をされていることも分かった。また、今回研修及び視察で感じたことは、キャストの方が笑顔で接客していて、お客さんを楽しませつつ、安全を考慮されているところや、街並みを見て、安全に心掛けていたところを感じることができた。
学生Mさん:事前学習を行い、ハウステンボスがSDGsでどのような取り組みを行っているのか知ることはできたが、現地に行かないとその規模があまり理解できなかった。しかし、今回の研修を通して、ハウステンボスで行われている下水処理能力がどのようなものであるか、理解することができた。基準では二次処理の段階で外に放出してもよいとされているが、ハウステンボスはさらに上の三次処理まで行っていることに驚いた。安心と安全は別物という話を聞いて、その通りだと感じた。実際に園内を歩いていると、たくさんの植物が育っていたが、園内で下水処理を行い、その水を再利用して育ったものだと思うと、大規模な取り組みだと感じた。
学生Bさん:ハウステンボスでは、単なるテーマパークではなく、多くの人が定住できる都市を目指して昔から環境設備に力を入れてきたそうだ。特に印象に残った環境設備として、共同溝と呼ばれる地下トンネルである。共同溝は、景観を損なわなかったり、自然や災害に強かったり、非常に環境に配慮したものであるが、一つの環境設備を造るのには、それを維持していく方法や計画を考える必要があり、多くの人の協力があってからこその環境設備なのだなと実感することができた。