「家庭経営学」の授業で、A4・1枚で伝える究極のレポート発表会を実施しました!
7月17日(水)、中・高家庭科教員免許の取得を目指す栄養科学科の3年生を対象にした「家庭経営学」の授業の中で、A4・1枚で伝える究極のレポート発表会を実施しましたので、報告いたします。

「家庭経営学」は、免許状取得のための必修科目の一つで、「人間の生活を家庭と社会とのかかわりとして扱う魅力的な学問」です。家庭経営学を学びはじめてから、「自分を取り巻く社会の課題が見えてきた」と感じる学生が多く、知的に面白いこの科目への関心は次第に高くなり、学期末に位置づけられたこの発表会でどういうテーマを取り上げるか、発表のかなり前から思い悩んでいたようです。
今年度の受講学生10名が取り上げたテーマは、次のとおりです。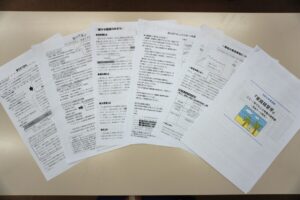
<題目>
第一席「ギフテッドについて」
第二席「夫婦別姓」
第三席「母子カプセル」
第四席「親の過干渉による子供への影響」
第五席「男性の育児参加について」
第六席「DEWKSについて」
第七席「ヤングケアラー」
第八席「生涯独身率と事実婚について」
第九席「女性の社会進出」
第十席「様々な結婚のかたちについて~別姓、週末婚など~」
発表の持ち時間は、1人あたり7分です。わずか7分と思われるでしょうが、4分きっかりに発表をおさめ、それに続く3分間の質疑応答に耐えうるものでなければなりません。7分を過ぎると、聴衆の側の学生は、わずか2分間で相互評価票を書き終えるのです。緊張感が漂う教室でしたが、自分たちがまだよく知らない社会的課題に出会う場となり、家庭科教諭として、今後、教壇に立つ者としての「覚悟と心ばえ」ができた時間となったようです。
下に、このレポート発表会を終えた学生の声をいくつか紹介してみます。
<学生の声>(抜粋)
Aさん:家庭科に関する社会問題は様々あるなと感じました。以前と現在では、法律が改正されたり、新しい法律や制度ができたりして日々変わっていくため、
自分で追究していかないといけないと思いました。
Bさん:教師になる立場として、様々な家庭の児童生徒がいることを考慮しながら接し、授業でも発言に気を配らなければならないと感じました。
Cさん:普段の生活では疑問に感じない部分の話題を取り上げていておもしろかった。身の周りでは、多くの問題や課題があることに気付くことができた。
Dさん:家庭科教員になった際には、一人でこれ以上の情報を手に入れていかないといけないので、普段から様々な角度にアンテナをはっておく必要があると
改めて思いました。

発表の様子

質疑応答の様子

質疑応答の様子


